12/3はプレイステーションの発売日。今年は20周年だと!?・・・10年くらいかとおもってた・・・。
ということでこの機会にプレイステーション(初代)の思い出でも語ろうかなと思いましたが、メタルギアやらFF7やらバイオハザードやらレジェンドなソフト達を語るのもいいですが語り尽くされている感あるのでここは一つマイナー気味のソフトについて語ってみたいともいます。
スペースグリフォンVF-9
はいこちら。FPSというジャンルは今となってはハイエンドゲーム機のメインジャンルかと思いますが、当時はまだそんなにメジャーではありませんでした。このゲームはFPSというよりもロボットを操縦して探索するアドベンチャー的なものですが。プレイステーションでゲームが2Dから3Dに進化し、新たな映像体験が得られるようになったことと、CDという大容量メディアの登場によってフルボイスが実現したことなども相まって感動したものでした。「ゲームで酔う」という感覚を初めて味わったのはこれかもしれない。結構ストーリーはハードだった気がします。そうゆうシリアスなストーリーが味わえるようになったのもゲームの進化ですね。
戦国サイバー藤丸地獄変
YouTubeにめぼしい動画が上がっていないことからして、けっこうマイナーなゲームではないかとw
SCEが出したシミュレーションRPG(ファイアーエムブレム系)のゲームです。
その名の通り和風テイストですが、本編の合戦パートの後は隠れ里での育成モードというのがあってパワプロのサクセスモードとかあの系統の育成が楽しい要素があって楽しかったです。
史実と違って忍者が侍よりも強い影響力を持っている世界として描かれ、戦国時代でありながらミサイルやレーザー、バーニアなどといった近代兵器が「からくり」として登場し、物語は戦国ファンタジーとして展開していく。
体力が0になってしまったキャラクターの蘇生が不可能、攻撃やキャラに付けられている属性をゲーム中で確認できない、戦闘マップでの途中セーブ不可、複数面にまたがる一部のマップでは人選が変更不可(特定の仲間を引き連れていないと行えないイベントもある)など、難易度は高い。
さらに真のエンディングを見る場合、全てのキャラを仲間にして全員生存させ、隠しマップを全てクリアするなど、複数の条件を満たさなければならず、難易度が跳ね上がる。
フィロソマ
ジャンルはシューティングゲームなのですが、やたら映像と映像が凝っていて1本のSF映画を見ているような構成です。↑はゲームのオープニングムービー。長すぎるw プリレンダリングのムービーには当時衝撃を受けました。プリレンダってのはつまりデータ容量さえあればゲーム機のスペックも関係ないのですが、このような映像が見れる事自体衝撃的でしたからね。
やたら凝ってるんすよストーリーが。ただのシューティングゲームなのにw(失礼)これ発表されてから発売延期を繰り返して相当力入れて作ったんだと思うんですけどね。
肝心のゲームパートはシーンごとに横スクロールになったり縦スクロールになったりスペースハリアーみたいなったりとこれまた無駄に(w)凝っていて、力のかけどころがおかしな方向に行ってしまった愛すべきゲームという感じで。このストーリーのオチも凝っているので機会があればプレイして頂きたいw
テーマパーク
これはいわゆる「洋ゲー」の一種かな。今は洋ゲーがメインストリームだが当時は洋ゲーは珍しかった。わざわざSCEが「洋ゲー」キャンペーンを打つくらいに。
このゲームは簡単に言うとシムシティの遊園地板といったところなのですが、パーク内が汚くなってくると客がゲ◯っぽい声を出すのが妙にリアルで困ったということで印象に残っています。うん。
TOTAL NBA ‘96
こう見えて実は中学はバスケ部だったのですがこのゲームは皆で集まってよく遊びました。
コートに脚が反射している!キュッキュ鳴る!っていうリアルさにまず衝撃を受け、外国人の実況ボイスと実名の選手たちのリアリティに本物のNBAの中継さながらの雰囲気を味わえました。
このゲームでNBAの選手とか色々覚えてましたね。「ミッチリッチモンドはミッチで区切る」とかw 当時はネットという情報源も無いので、テレビであまり放送されないNBAの情報って断片的でしたから。デニス・ロドマンのモデルの頭だけ色ついてたのが印象的w
Three Point Basket!!
MOON
戦闘のないRPG。世界観に浸るという楽しさ。
ゲームにおける作品性とか作家性みたいなものを初めて感じた作品かもしれません。
当時、AVマルチっていう端子でテレビに繋いでくっきりした映像に感動してた気がする。まだもちろんHDもない時代。エンディングの仕掛けに驚いて友達に勧めたくなる作品。
バスト・ア・ムーブ
パラッパラッパーやビートマニアではなくあえてこれを挙げましょう。
対戦格闘的にダンスをする音ゲーですが、モーションキャプチャーってすげーんだなってのを感じた作品の一つ。 ダンスした気になれる楽しさがあります。
Perfect Performer
イエモンファンだしこれは外せない・・・てかこのゲームやったこと無かったw
たぶん今後もやる機会は無いであろうw



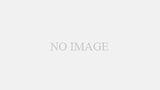
コメント